4月2日(日)晴れ
参加者:28名 男性9名 女性19名(うち一般参加者女性6名)
コースタイム:鈴蘭台駅9:00〜菊水山登山口9:20〜菊水山山頂10:20[お天気講座①]11:20〜鍋蓋山山頂12:10[昼食・お天気講座②]13:30〜再度公園13:45[コーヒータイム]14:25〜諏訪山公園15:30
雲ひとつ無い(と朝は思っていた)空のもと一般の方も交えてのお天気入門ハイクが始まった。
私自身も観天望気は初めてででワクワク!
登山口で皆で体操‼︎今日は大所帯の28名で4班に分かれて出発した。
菊水山でお天気の講座の始まり〜。雨が降るメカニズムや雲のできる仕組みのお話。
そこで朝は「雲ひとつ無い」と思っていた事が間違いであると学んだ。今朝の空の様子は空に浮かんでいるような雲はなかったが真っ青な空でもなかった。それは薄っすらと白いベールのような雲=巻層雲=がかかっている状態であると…。
そして朝はなかった綿雲のような雲=積雲=が少しずつ出始めて来ていた。それは時間の経過とともに地表や空気の温度、湿度がどんどんと変化して起こる事なのだと。30分でずいぶんと賢く(笑)
バテそうになりながら鍋蓋山を登りお昼ご飯で元気を取り戻しお天気講座第2部の始まり。
ここでは雲観察カードを記入して雲の様子を再確認。
合ってるかな?と先輩のカードを覗き見^_^;
紀伊半島上空にはロール状の雲=層積雲=がかかっていた。菊水山では少しだった積雲もどんどん増えて来て弱い北風にのって南の方角に流れていた。高く伸びた樹木を基準にみると速度がよりわかりやすい。天気の移り変わりを感じここでも更に賢くなりました(笑)
再度公園でホッとひと息。楽しかった1日を班ごとに振り返りました。
時間や距離が長い山行ではなかったけど充実した実り多い1日となった。
明日から空を見上げるのが楽しみになりそうだ^_^






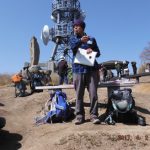



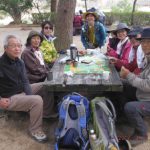

















ミツマタ-150x150.jpg)














